「捕まえて、また放す」 ― ベトナムに根づく共生のかたちとは?

「捕まえて、また放す」 ― ベトナムに根づく共生のかたちとは?
ベトナムの街を歩いていると、ふと目にする光景があります。
市場の一角で、鳥かごの中にたくさんの小鳥たち。そのすぐ隣で、人々が小さな手でその鳥を空へと放しているのです。
「捕まえて、また放す」— 一見矛盾しているように見えるこの行為の中に、ベトナムの人々が持つ“いのちとの距離感”が静かに息づいています。
功徳と感謝の風習
この風習は「放生(phóng sinh)」と呼ばれ、仏教の教えに由来します。
命を救うことで功徳を積み、同時に「生きとし生けるもの」への感謝を示す — そんな祈りが込められています。
寺院の前では魚やカメを川に放つ人々の姿が見られ、旧正月には、台所の神を天に送り出すために金魚を放す習慣もあります。
それは季節の風物詩として、今も人々の暮らしに根づいているのです。
変わりゆく放生のかたち
しかし近年、この「放生文化」も新たな課題に直面しています。乱獲や不適切な放生により、外来種が生態系に影響を及ぼすことも。
それでも、人々がそこに込めた“いのちを思う心”まで否定することはできません。
大切なのは「形」ではなく、「想い」。
命を尊び、自然と調和しようとする祈りが、今も息づいています。
“放す”という自由の意味
ある動物保護団体の代表はこう語ります。
「本当の“放す”とは、野に帰すことだけでなく、恐れや支配からも解き放つことだと思う。」
その言葉の通り、ベトナムの人々は「支配」ではなく「共に生きる」という感覚を大切にしています。
野良犬や野良猫にエサを与える人も、放生を行う人も、根底にあるのは同じ“共感”と“祈り”なのです。
“いのちと共にある”という哲学
「捕まえて、また放す」—それは単なる宗教的儀式ではなく、長い時間をかけて育まれてきた、ベトナムのやさしい哲学。
一度つかんだ命を再び自由にするという行為の中に、人と動物が共に生きるという理想が映し出されています。
それは、いのちを敬い、いのちに寄り添うこの国ならではの祈りのかたちなのです。
執筆者:Meizz0123
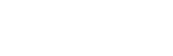









この記事へのコメントはありません。